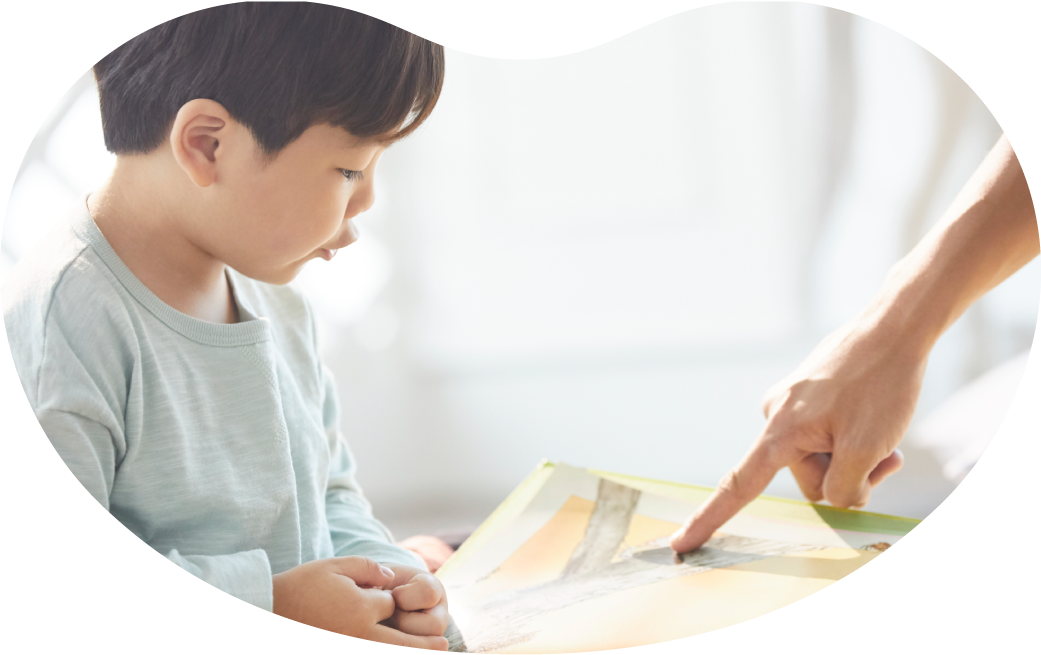



凹凸凸凹保育園浦和西口校はJR浦和駅西口徒歩10分の場所にある未就学児のお子様をお預かりする定員10名の児童発達支援施設です。
保育園のように、預けて、任せられる「保育型療育」をコンセプトにしています。
「療育」や「発達支援」という言葉を聞き慣れないと児童発達支援施設は敷居が高く感じるかもしれませんが、私たちは保育・療育のプロなので安心して遊びに来る感覚で、子育ての不安や心配事をお気軽に相談しに来てくださいね。
施設情報
| 施設名称 | 保育型児童発達支援 凹凸凸凹保育園浦和西口校 |
|---|---|
| 種 類 | 児童発達支援施設 |
| 住 所 | 〒330-0064さいたま市浦和区岸町7-3-10岸町コーポ1階 |
| 電話番号 | 048-711-9926 |
| 最寄駅 | JR浦和駅西口徒歩10分 |
| 保育時間 | 月-金 9:00-16:00 |
| 保育年齢 | 0歳児-5歳児まで |
| 定 員 | 10名/1日あたり |
| 支 援 プログラム |
資料はコチラ |


























利用について
見学できます。凹凸凸凹保育園では定期的に見学説明会を開催しております。また、遠方からお近くに転居予定の方や、ご多忙の方のために個別に日程を調整して行う個別見学説明会も行っております。凹凸凸凹保育園にご興味をお持ちいただけましたら、まずはお気軽にいずれかの説明会にご参加ください。
併用できます。実際にお子様が通われている幼稚園や保育園の集団生活や生活リズムを念頭に置きながら、お子様の発達に応じた支援を行います。お子様が通われる幼稚園・保育園さんに施設のスタッフがお伺いして連携を取ることも可能です。
週1日からご利用いただけます。お子さまの受給者証で定められたサービス提供量を上限に、利用頻度は週1日~5日になります。
他の施設とも併用いただけます(ただし、同じ利用日に複数の施設利用はできません)。お子様の発達に応じた連続した療育が展開できるよう併用される施設とも連携を取りながら個別支援計画をつくり、保育を実践します。
凹凸凸凹保育園は、「発達の遅れが気になる」「発達障害の可能性があるかもしれない」段階から利用できるさいたま市指定の児童発達支援事業所です。障害者手帳や医学的な診断の有無を問いません。児童発達支援で早期支援を受けたことで小学校の通常学級に進学していく例もたくさんあります。
はい。施設内に給食室があり、凹凸凸凹保育園の調理員が栄養士監修のもと工夫を凝らしたオリジナル献立の給食を毎日提供しています。小規模保育施設の良さを活かして、調理時に固さや大きさ、アレルギー対応まで個別にアレンジします。 認可保育園の基準で栄養給与量を計算管理し、偏食や感覚過敏のあるお子さまにも、丁寧に対応します。
障害に関する手帳や障害の確定診断の有無に関わらず、発達に気がかりなところがある乳幼児がご利用いただける施設です。個別的な支援が望ましい未就学児のお子様に早期療育を行います。
障害に関する手帳の有無や診断、障害の確定を問わず、発達に気がかりなところがある乳幼児がご利用いただける施設です。小学校就学前の主に2〜5歳児の、個別的な支援が望ましいお子さまのために早期療育を行います。
利用日の午前9時〜9時半までの間に、お子さまと一緒に当教室までお越しいただきます(登園)。その後、保育園や幼稚園と同じように、教室でお子さまをお預かりし(親子分離)、他のお友だちや先生たちと一緒の小さな集団の中で、遊びやお散歩、給食、休息、設定保育、個別タイムなどお子さまの個別支援計画にあわせた日々の活動を通じて療育を行います。15時半〜16時までに保護者の方にお迎えにお越しいただき、その日の活動内容を記録した「サービス提供記録票」にサインいただいて終了(降園)となります。
受給者証について
受給者証とは自治体から交付される福祉サービスの利用対象であることの証明書です。受給者証を取得することで、児童発達支援の利用料9割の公費負担(保護者負担 1割)が受けられます。受給者証には保護者と児童の氏名、生年月日、住所、サービスの種類、その支給量(日数や時間数)が記載されます。
療育手帳とは障害名や程度を証明するために都道府県が発行している証明書です。 受給者証は障害の内容や程度に関する証明書ではなく、あくまでも「福祉や医療のサービスを(公費負担を受けて)利用できる証明」として市町村が発行しているものです。 そのため、受給者証を持っているからといって障害が確定・診断されているということではありません。
受給者証に記載される支給量とは、自治体が認めた福祉サービスを利用できる日数や時間数のことです。例えば受給者証に支給量が「20日/月」と記載されている場合には「ひと月あたり最大 20日まで児童発達支援を利用できます」という意味です。支給量に応じたサービス利用料の9割を自治体が負担することになるので、月に何日利用できるかは自治体の福祉窓口と相談をして決めることになります。自治体ごとに判断が異なる場合もあるので、お子様の発達の状況や特性、利用を考えた経緯、希望する利用時間や日数を自治体の担当者に詳しく伝えることが大切です。
受給者証の交付はお住まいの自治体の福祉窓口で申請します。自治体により申請方法や流れが多少異なりますので、詳しくは施設までお気軽にお問い合わせください。
必要ありません。児童発達支援は受給者証があれば、療育手帳を取得していないお子様でも利用できる福祉サービスです。
受給者証のみ申請・取得することが可能です。お住まいの自治体の福祉窓口に問い合わせてください。自治体により申請方法や流れが多少異なりますので、詳しくは施設までお気軽にお問い合わせください。
受給者証がなくてもご利用はいただけますが利用全額が自己負担となります(1日あたり 1万円以上の料金負担が生じます)。また、療育手帳だけでは、受給者証をお持ちでない場合と同様となります。
申請が必要です。転居先の自治体の福祉窓口にお問い合わせいただき、申請の手続きを行ってください。